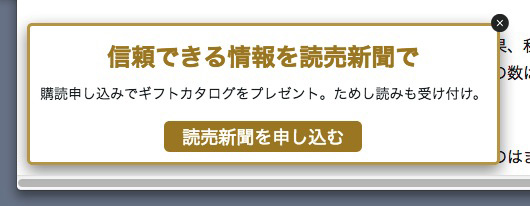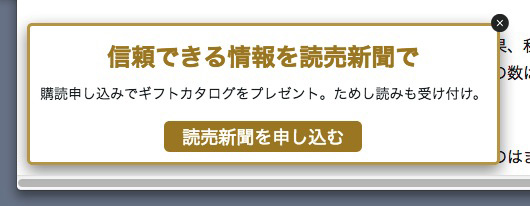| |
読売新聞戦争責任検証委員会『検証 戦争責任』, 中央公論新社, 2006. 第八章
|
世論形成 新聞、報道の使命放棄
満州事変 (三一年九月) は、日本のジャーナリズムにとっても、大きな分岐点だった。
満州事変後、新聞各紙は、特派員を大勢派遣し、軍部の動きを逐一報道した。
それにあおられるようにして、国民は好戦的になっていった。
「満蒙は帝国の生命線であり、必ず守らなければならない」という世論は、新聞によって形成されたとみてよい。
新聞各紙とも、満州国独立構想、リットン報告書、国際連盟脱退などを追い続け、戦況報道によって部数を飛躍的に伸ばしていった。
利潤の追求が、言論機関としての使命より優先されていった。
関東軍が、満州国に国民の支持を得ようと、新聞を徹底的に利用しようとしたのも確かだ。
しかし、軍の力がそれほど強くなかった満州事変の時点で、メディアが結束して批判していれば、その後の暴走を押しとどめる可能性はあった。
二・二六事件を経て、日中戦争が始まると、言論統制は急速に強化される。
慮溝橋事件発生後、華北への派兵を決定した近衛内閣が、メディア代表を集めて挙国一致に向けた協力を求めるなど、政府は宣伝戦に力を入れ、新聞側も、基本的にこれに歩調を合わせた。
日米開戦の導火線となる日独伊三国同盟の締結や南部仏印進駐などのたびに、各紙の紙面は礼賛記事で埋め尽くされた。
新聞社内には、そうした風潮に批判的な声もあったが、結果として、無謀な対米英戦へと国民を誘導していった。
代表的な言論人に徳富蘇峰がいた。
大日本言論報国会会長として「言論統制そのものに寄り添い、戦争遂行を支援」{米原謙『徳富蘇峰』中公新書) した。
真珠湾攻撃の二日後に開かれた新聞各社共催の「米英撃滅国民大会」では、大東亜戦争は「義戦」と講演した。
日米開戦の日に、内閣情報局が、戦況報道は大本営発表以外は一切掲載禁止とする、と示達した。
公式発表に疑問があっても独自の記事を掲載するには、廃刊の覚悟が必要になった.
戦意をあおる扇情的な見出しをつけ、大本営発表がウソだとわかっていながら、そのまま報道し続けた。
言論・報道の使命をまったく放棄していた。
|
|
読売新聞は,「新型コロナ」報道においてこれをなぞっている。
皮肉なもんである。
実際,ひとは他人を批判するが,自分がその者の立場になればその者の行いをするのである。
「他山の石」「ひとの振り見てわが振り直せ」は空言,というわけだ。
「検証 戦争責任」は役に立たない,というわけだ。
いまの読売新聞が大東亜戦争の新聞と違うところは,
| 《 |
公式発表に疑問があっても‥‥‥戦意をあおる扇情的な見出しをつけ、
大本営発表がウソだとわかっていながら、そのまま報道し続ける》
|
のが,「言論統制」が理由ではなく,引っ込みがつかないことが理由だという点である。
大本営の<引っ込みがつかない>と同じである。
読売新聞の Webサイトにアクセスすると,つぎの「信頼できる情報」タグが現れる:
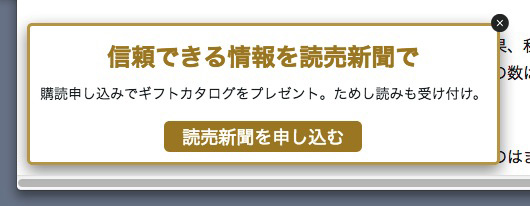 笑止千万なり。
笑止千万なり。
|