氷河が同じ姿であるとは,つくると消えるが均衡しているということである。
氷河が後退しているとは,氷河がつくられていないということである。
氷河をつくるものは,雪である。
そして,雪のもとは雲である。
よって,氷河が後退しているとは,雲が少なくなっているということである。
<雲減少 → 雪減少 → 氷河後退>である。
ひとは,<気温上昇 → 氷河後退>だと思っている。
氷河後退を「氷河が融ける」だと思っているのである。
事実は,氷河後退は「氷河をつくる雪が降らない」である。
「氷河が融ける」を取り上げるにしても,その因果は<雲減少 → 日照量増加 → 氷河周辺温度の上昇 → 氷河が融ける>である。
そしてこの「氷河が融ける」は,「氷河がつくられない」に比べて桁違いに小さい。
無視してよいものである。
よって,繰り返すが,<雲減少 → 雪減少 → 氷河後退>である。
因果関係を間違わぬよう。
こうして,気候変動は,雲量変動として考えることになる。
そこで問題は :
雲量変動の系は複雑系である。
この問題の解は,シンプルではあり得ない。
それでも,シンプルな主調を考えたくなる。
科学は,ここをがんばりどころにする。
そのようなトライとして,ここに Bond (2001) を引く。
Bond (2001) は,北極気候変動が太陽活動に連動していることを,データで示す:
北極気候変動を,年代ごとの<氷河が海域Aへ運ぶ礫の量>に表現する。
太陽活動を,磁場変動として,年代ごとの<炭素14 (14C) とベリリウム10 (10Be) の量>に表現する。
この2つの表現は,つぎのように重なる:
礫量 ─ 14C 量
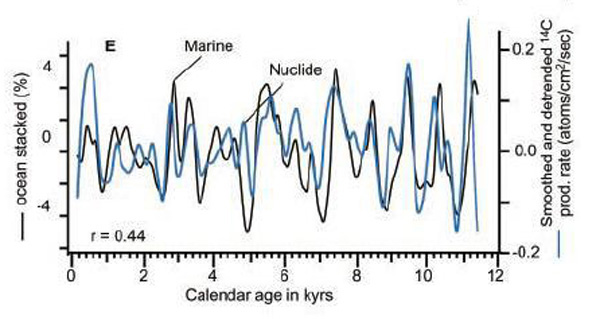 礫量 ─ 10Be 量
礫量 ─ 10Be 量
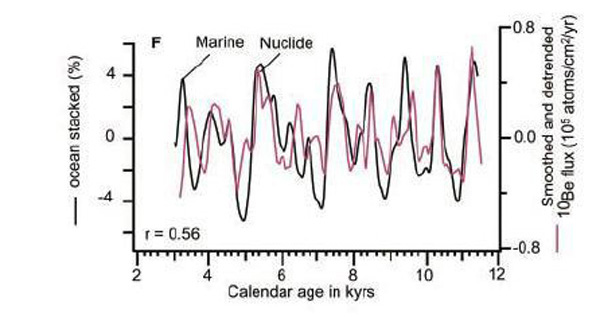
太陽活動と氷河生成は,どうつながるか?
こういうストーリーになる:
太陽活動が弱る
→ 地球を覆う太陽磁場の宇宙線遮蔽力が弱り,地球に降り注ぐ宇宙線量が増加
→ 雲量が増加
→ 雪増加
→ 氷河前進
太陽活動が強まる
→ 地球を覆う太陽磁場の宇宙線遮蔽力が強まり,地球に降り注ぐ宇宙線量が減少
→ 雲量が減少
→ 雪減少
→ 氷河後退
ここで<宇宙線 → 雲>は:
<宇宙線 → 二次宇宙線 → 微粒子=雲核 → 雲>
さて,<宇宙線 → 二次宇宙線 → 微粒子=雲核 → 雲>は本当か?
仮に本当だとして,こうしてつくられる雲は,氷河をつくるのに必要な雲量とどんな関係に?──決定的関与なのかそうでないのか?
この問題は,ここではペンディングとするのみである。
- 引用文献
G.Bond, et al. (2001) :
Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene,
Science, vol.294, 2001. pp.2130-2136.
- 参考Webサイト
|